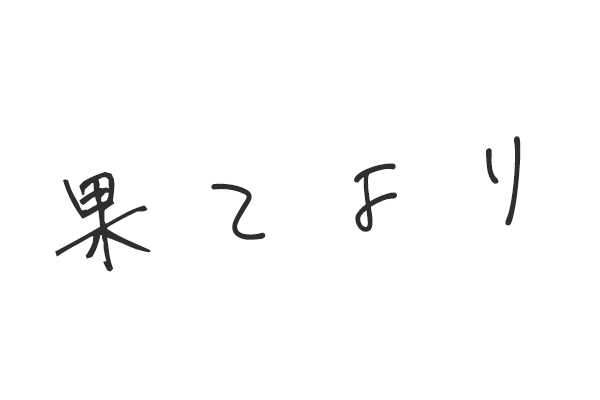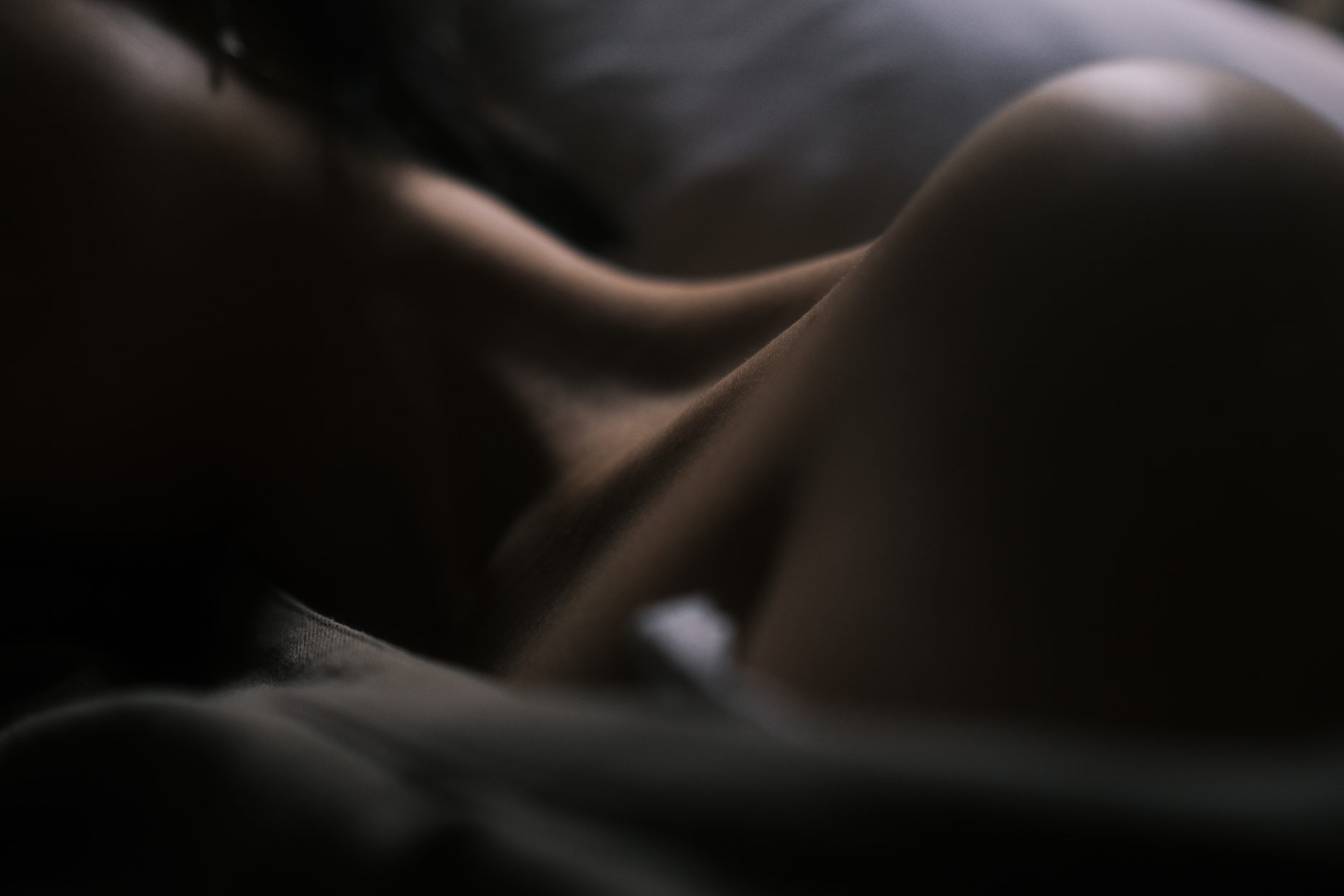真夜中の暗い部屋の中で、僕は君にふれた。その部屋は古びていて、少し埃と畳の匂いを漂わせながら、それでも、暗い部屋の中でジャズバラードを流して肌を重ねて、この世の果てにいるような気分で、僕は君にふれる。
窓の隙間から聴こえてくるスナックのカラオケの音が遠くに聴こえて、現実と非現実の狭間で僕達は、時に笑みを見せながら、時に感じあいながら、誰にも邪魔されることのない明かりを消した部屋でキスをする。
あの日のことが、今では不思議な感覚となって、現実のことだったのか、夢だったのか、薄れていきます。
ただ、帰り際に手渡された、「死なないで」というメモ書きを渡された文字を見て、もう少し生きないといけないなぁと感じながら、あの紙がどこにあるのか、失くしたのか、やはり夢だったのか、よくわからなくなっています。
以前の手紙で、この世界は遅かれ早かれ終わりを迎えるでしょう。なんてことを言ったんだけど、今の僕は、もう少し生きて、あの日のことが夢だったのか現実だったのかを、確かめるためにも君に会わないといけないような感じもするのです。
蜂の巣のような都会では、数えきれないドラマが演じられては忘れ去られていくのでしょう。
僕達のあの日も、人知れず終わりを迎えては、当人達すら曖昧な記憶となり、消え去るのかも知れないですね。
だから、手紙を書きます。誰にでもない記憶の彼方へ
また、果てにいきましょう。
では、また。